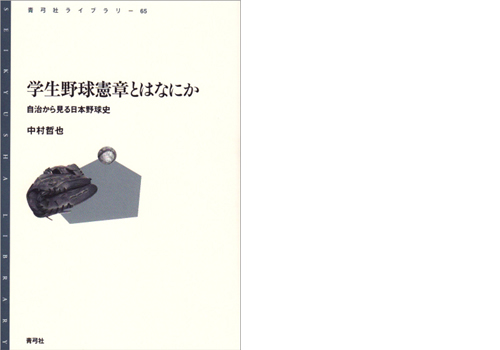日本野球の歴史がつまびらかに

学生野球憲章とはなにか
自治から見る日本野球史
中村 哲也 (著)
青弓社ライブラリー(2010年)1600円+税
当時の野球の繁栄の推移。著者は歴史家らしく、丹念に、著書のはじめから6章まで387項目もの豊富な史料を引用し、出典を明示しています。学生たちの努力で野球が広まっていった歴史は承知していたつもりでしたが、その社会的なフィーバーぶりは知りませんでした。
ラジオ時代のプレオグラフなるメディアも紹介されたり、戦後アメリカから入ったとばかり思っていたソフトボールらしきインドア・ベースボール(という戸外スポーツ)の大会が当時あったことなども……。このころ、このフィーバーにまつわる「学生野球の弊害」が現れるなかで、「学生野球の社会的ルールと全国的な組織をつくろう」との気運も募ります。
1932(昭和7)年に、文部省によって制定された「野球統制令」についても、統制令は3校以上が参加する大会やリーグ戦の開催には行政の許認可を義務づけるなど、学生野球に統制を示したが、一方、奨励の面もあり、地方体育団体の整備、公営野球場も建設がすすみ(静岡・草薙球場もその一つ)、インフラ面で野球の振興をおこなったと評価。「野球統制令の功罪」と捉えているのは、野球関係者の間での専らの害悪視とは一味ちがうように思いました。統制令の後、野球が敵性スポーツとされ、戦時下に弾圧される逆境で、国民の目の届かぬものになっていきます。そして、戦後の復活……。
いま高校生の特待生制度、プロと高校の交流など、学生野球憲章の見直しが注目されています。それに至る野球界の流れや取り組みがつまびらかです。ご一読をお薦めします。なお、著者は本誌の編集委員でもあります。(小柴晃)
リンク