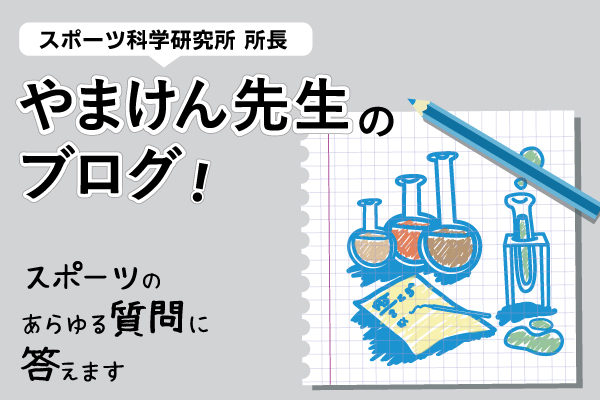

山崎 健(やまけん先生)
新日本スポーツ連盟附属スポーツ科学研究所所長。新潟大学名誉教授。専門分野は運動生理学、陸上競技のサイエンス。マスターズM65三段跳&3000m競歩選手兼前期おじいさん市民ランナー。
駅伝シーズンとなりましたが、テレビで放映される女子長距離選手は「細~い!」という印象を強く感じます。実はテレビ映像で「細い」と感じる選手の皆さんは、直接見ることがあると本当に細いのです(普通の体形の選手もテレビ放映では 「ガッチリ」 しているように見えます)。
食事にも気を使いながら月500~800km以上走りますので体脂肪率も低く、月間走行距離と5000mなどの記録との相関も指摘されています。

新谷仁美選手は、本人がSNSで発信しているように、2013年モスクワ世界選手権女子10000mで5位に入賞した際は、身長165㎝で体重40㎏、体脂肪率3%であったとのことですが、問題はこの時点で「無月経」であったことです。
そして一時期引退後再び2020東京五輪を目指し、2019年の日本選手権では2013年の記録を越える「日本新記録」で優勝していますが、実はこの時は「生理初日」だったそうです。新谷選手は自分のシビアな経験から、女子長距離選手が「無月経」となるようなトレーニング内容に対して選手や指導者に強い警告を発信しています。
女子アスリートのFAT(3主張)とは、①利用可能エネルギー不足(過度な栄養摂取制限)、②視床下部性無月経(体脂肪率12%以下で頻発)、③骨粗鬆症(生理周期に関わるエストロジェンというホルモン不足にともなういわば 「更年期並みの骨密度低下」)を指します。
当然日常の練習でのエネルギー消費を支えることはできませんので筋や免疫細胞の分解で「生存するため」のエネルギーを補填します。骨密度は更年期女性並みのレベルですので月800㎞を越える練習量では容易に「疲労骨折」を発症します。そして摂食障害は「絶食」とその反動での「過食と直後の嘔吐」を誘発します。
これらの問題点を理解していない(理解しようとしない?)指導者の間違ったトレーニングのガイドラインは、女子アスリートの心理的問題をも引き起こします。実はFATを発症しやすい心理的特徴は「完璧主義(1位以外は意味がない)」「(指導者に対しての)良い子志向」「自己抑制志向」などがあると言われています。
〈参考〉NHK『#アスリートは黙らない』2021年放映/『Health Management for FemaleAthletes-女性アスリートのための月経対策ハンドブック』東京大学附属病院 女性診療科・産科 2016年
「スポーツのひろば」2025年5月号より
